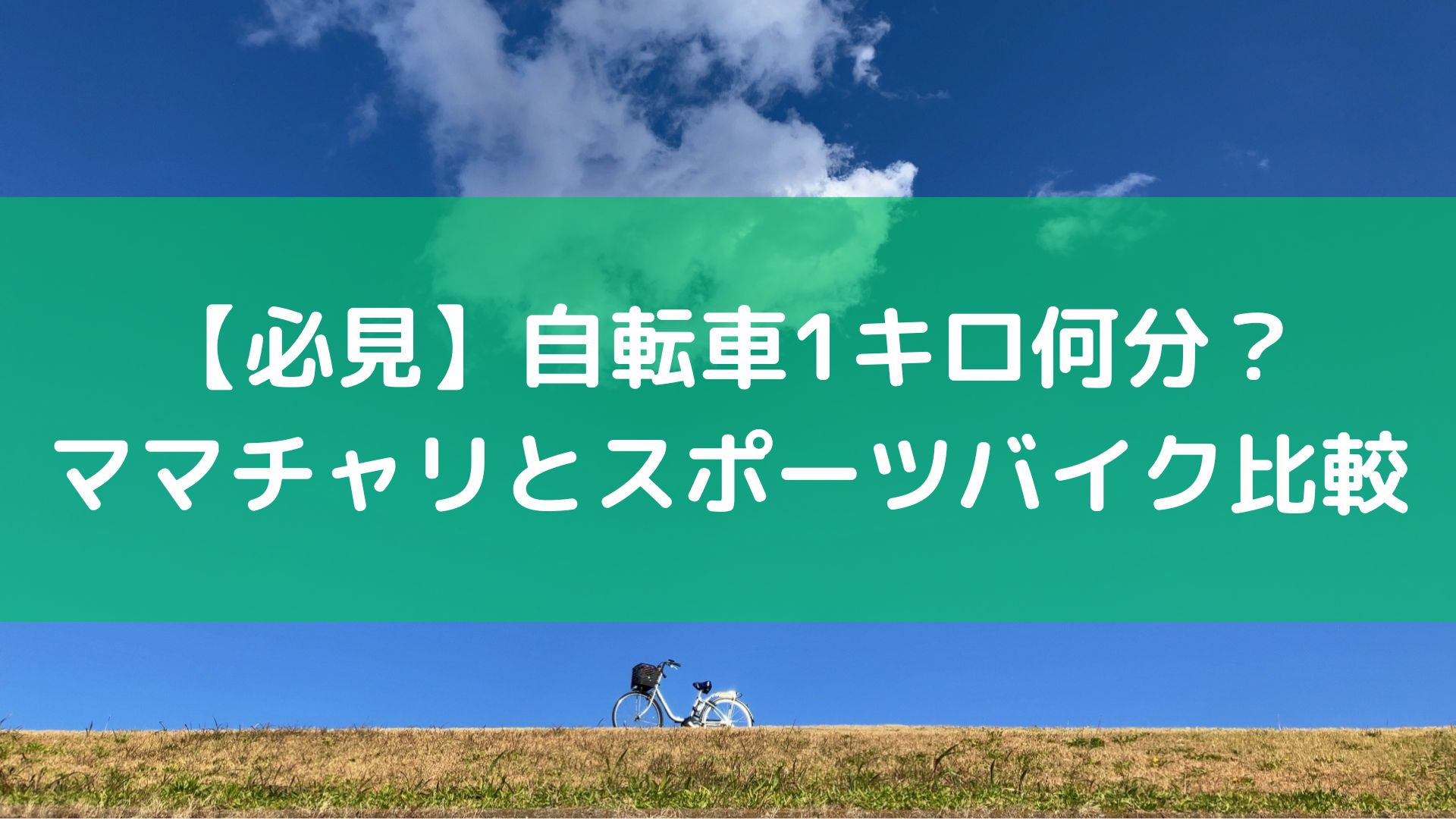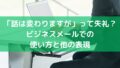「駅まで自転車で10分ぐらいだよ」と言われたとき、皆さんはどれくらいの距離を想像しますか?
実際に走ってみたら、思ったよりも遠くて驚いた経験があるかもしれませんね。
また、「駅まで5km」という場合、自転車で何分ぐらいかかるのか、すぐにはイメージしにくいものです。
そんなときに役立つのが、「自転車で1km進むには何分かかるか」という目安です。
この記事では、自転車での移動時間の感覚をつかむために、1km進む時間を中心に詳しく紹介します。
また、普段使いのママチャリと、スピード重視のロードバイクの違いについても比較していきます。
自転車で1キロ走るのに必要な時間は?
まずは、自転車で1kmを移動するのにどれくらい時間がかかるか見ていきましょう。
一般的な自転車の走行スピードは、時速12kmから18kmの間が多いです。
今回はわかりやすく、時速15kmを基準にして考えてみます。
時速15kmで走ると何分かかる?
時速15kmというのは、1時間で15km進むペースです。
これを計算すると、60分 ÷ 15km = 4分となります。
つまり、自転車で1km進むにはおよそ4分必要ということですね。
もし時速20kmで走れれば、1kmあたり3分ほどで移動できる計算になります。
自転車と徒歩、それぞれの距離と時間を比較!
次に、自転車と徒歩での移動を比べてみましょう。
ここで示すのは平坦な道を止まらずに走った場合の目安です。
信号待ちや坂道の影響は考慮していないので、実際には多少変わる可能性もあります。
距離ごとにかかる時間の目安
-
1km:自転車(15km/hで4分、20km/hで3分)、徒歩は約12分
-
2km:自転車(15km/hで8分、20km/hで6分)、徒歩は約24分
-
3km:自転車(15km/hで12分、20km/hで9分)、徒歩は約36分
-
4km:自転車(15km/hで16分、20km/hで12分)、徒歩は約48分
-
5km:自転車(15km/hで20分、20km/hで15分)、徒歩は約60分
もし5.5kmなど半端な距離を移動する場合も、基本の時間にちょっと加算するだけでOKです。
移動時間別に進める距離の目安
-
10分:自転車(15km/hで2.5km、20km/hで3.3km)、徒歩は約800m
-
20分:自転車(15km/hで5km、20km/hで6.7km)、徒歩は約1.6km
-
30分:自転車(15km/hで7.5km、20km/hで10km)、徒歩は約2.5km
-
40分:自転車(15km/hで10km、20km/hで13.3km)、徒歩は約3.3km
-
50分:自転車(15km/hで12.5km、20km/hで16.7km)、徒歩は約4.2km
-
60分:自転車(15km/hで15km、20km/hで20km)、徒歩は約5km
日常の通勤や通学でかかる時間を考えると、20分以内がちょうどいい目安です。
その場合、自転車なら5km前後、徒歩なら1.5kmほどが現実的な範囲となります。
最近は自転車通勤を選ぶ人も増えていて、片道15km以内なら十分に実用的といえるでしょう。
自転車の種類で時間が変わる!ママチャリVSスポーツバイク
次は、使う自転車によって移動時間にどれくらい差が出るのか見てみましょう。
ママチャリとスポーツバイクの性能差
ママチャリは、街乗り用に作られた自転車で、快適さを重視しています。
スピードは時速15kmくらいで走るのが一般的です。
対して、ロードバイクやクロスバイクなどのスポーツタイプの自転車は、速さに特化して作られており、時速20km以上で走行可能です。
そのため、同じ距離でもスポーツバイクならママチャリより短い時間で到着できます。
都市部では速度差が縮まる理由
ただ、都市部の移動となると話が変わります。
信号待ちや人の多さ、交通量の影響で、スポーツバイクのスピードも大幅に落ちることがよくあります。
そのため、短い距離の移動では、ママチャリとスポーツバイクの到着時間に大差がつかないことも珍しくありません。
長距離ならスポーツバイクが断然有利!
一方で、長い距離を走る場合は、スポーツバイクの強みがしっかり発揮されます。
たとえば10kmの移動なら、ママチャリでは約40分かかるところ、スポーツバイクなら30分程度で済みます。
15km走る場合でも、ママチャリだと1時間近く必要ですが、スポーツバイクなら45分前後で到着できます。
しかも、ママチャリは重量があるため、上り坂やデコボコ道で速度がぐっと落ちます。
これに対して、軽量なスポーツバイクはギアの調整も効きやすく、坂道でもスムーズに走れます。
移動距離が長くなればなるほど、両者の時間差はどんどん大きく広がっていくのです。
効率的な自転車移動とは?時間と距離のベストバランス
自転車での移動が効果的かどうかは、目的や移動距離によって大きく変わります。
たとえば、都市部での短距離移動と、毎日の通勤や通学で使う場合では、求められる条件が違ってきます。
ここでは、どのようなシーンで、どれくらいの距離や時間がベストとされるのかについて、くわしく紹介していきます。
都市部での自転車利用に適した時間と距離
都市部での移動手段として自転車を使う場合、5キロメートル程度の距離がちょうどよいと言われています。
この距離をママチャリやスポーツバイクで走ると、所要時間はだいたい20分前後となります。
一方で、自動車を使った場合、同じ5キロメートルの移動ならば5分ほどで到着できることもあります。
しかし都市部では、交通量が多く、渋滞や信号待ちの影響を受けやすくなってしまいます。
そのため、自転車なら信号以外では止まる必要もなく、スムーズに移動できるので、実際には自動車よりも早く着くケースも珍しくありません。
とはいえ、都市部の道は人も多く、信号も多いため、プラス10分から20分程度の余裕を持ったスケジュールを立てることが大切です。
通勤・通学で使う自転車の適正距離と所要時間
毎日の通勤や通学で自転車を利用するなら、移動距離と所要時間をしっかり把握しておくことが重要です。
特に、朝の出発時間や帰宅後のスケジュールに影響するので、正確な目安を知っておきましょう。
以下は、信号や坂道が少ない平坦なルートを走った場合の、ママチャリとスポーツバイクそれぞれの目安時間です。
| 距離(km) | ママチャリ(所要時間) | スポーツバイク(所要時間) |
|---|---|---|
| 5km | 約20分 | 約15分 |
| 10km | 約40分 | 約30分 |
| 15km | 約60分 | 約45分 |
| 20km | 約80分 | 約60分 |
5キロメートル以内であれば、ママチャリでもストレスなく通勤・通学できます。
しかし、10キロを超えると体力的な負担が大きくなるため、スポーツバイクの軽快さとスピードが大きな利点となります。
15キロ以上の長距離では、スポーツバイクでないと時間も体力も消耗が激しくなってしまうため、ロードバイクのような車種の使用を強くおすすめします。
通勤や通学先までの距離に応じた適切な自転車を選びましょう。
歩いて1km進むには何分かかる?
自転車移動だけでなく、歩行での移動時間についても知っておくと、より移動手段を選びやすくなります。
一般的に、大人が歩くスピードは時速5キロメートル程度とされています。
この速度から計算すると、1キロメートルを歩くのには約12分かかります。
つまり、徒歩の場合は、自転車の約3倍から4倍ほど時間がかかるということになります。
急ぎの用事や、時間が限られている場合は、徒歩よりも自転車を使った方が圧倒的に効率的です。
移動時間を短縮したいときには、自転車の利用を積極的に検討しましょう。
電動アシスト自転車ならどれくらい速い?
最近では、通勤や子育ての移動手段として、電動アシスト自転車を選ぶ人も増えてきました。
電動自転車は、ペダルをこぐ力を電動モーターが補助してくれるため、長距離移動や坂道での負担が大幅に減ります。
一般的なママチャリが1キロあたり約4~5分かかるのに対し、電動自転車なら約3~4分で進めるとされています。
特に坂道の多いエリアでは、通常の自転車と比べても疲労感が少なく、移動時間のブレも少ないのが大きなメリットです。
交通量が多く、信号や坂道が頻繁に登場するような都市部では、電動アシスト自転車が非常に便利な選択肢となります。
【必見】自転車1キロ何分?ママチャリとスポーツバイク比較のまとめ
移動手段を選ぶときには、移動距離と目的地までの所要時間を意識することが大切です。
以下の表に、1キロメートル移動する際の各手段の目安時間をまとめました。
| 移動手段 | 1kmあたりの所要時間 |
|---|---|
| 徒歩 | 約12分 |
| ママチャリ | 約5分 |
| 電動アシスト自転車 | 約3~4分 |
| スポーツバイク | 約3分 |
5キロメートル以内の距離なら、ママチャリや電動自転車で無理なく移動できます。
10キロ以上の長距離通勤や通学では、より軽量でスピードが出るスポーツバイクを活用するのがおすすめです。
また、歩行や自転車だけでなく、電車やバスと組み合わせた移動方法も考慮して、効率のよい移動手段を選びましょう。
無理なく快適に移動できるよう、ライフスタイルに合った乗り物選びをしていきたいですね。