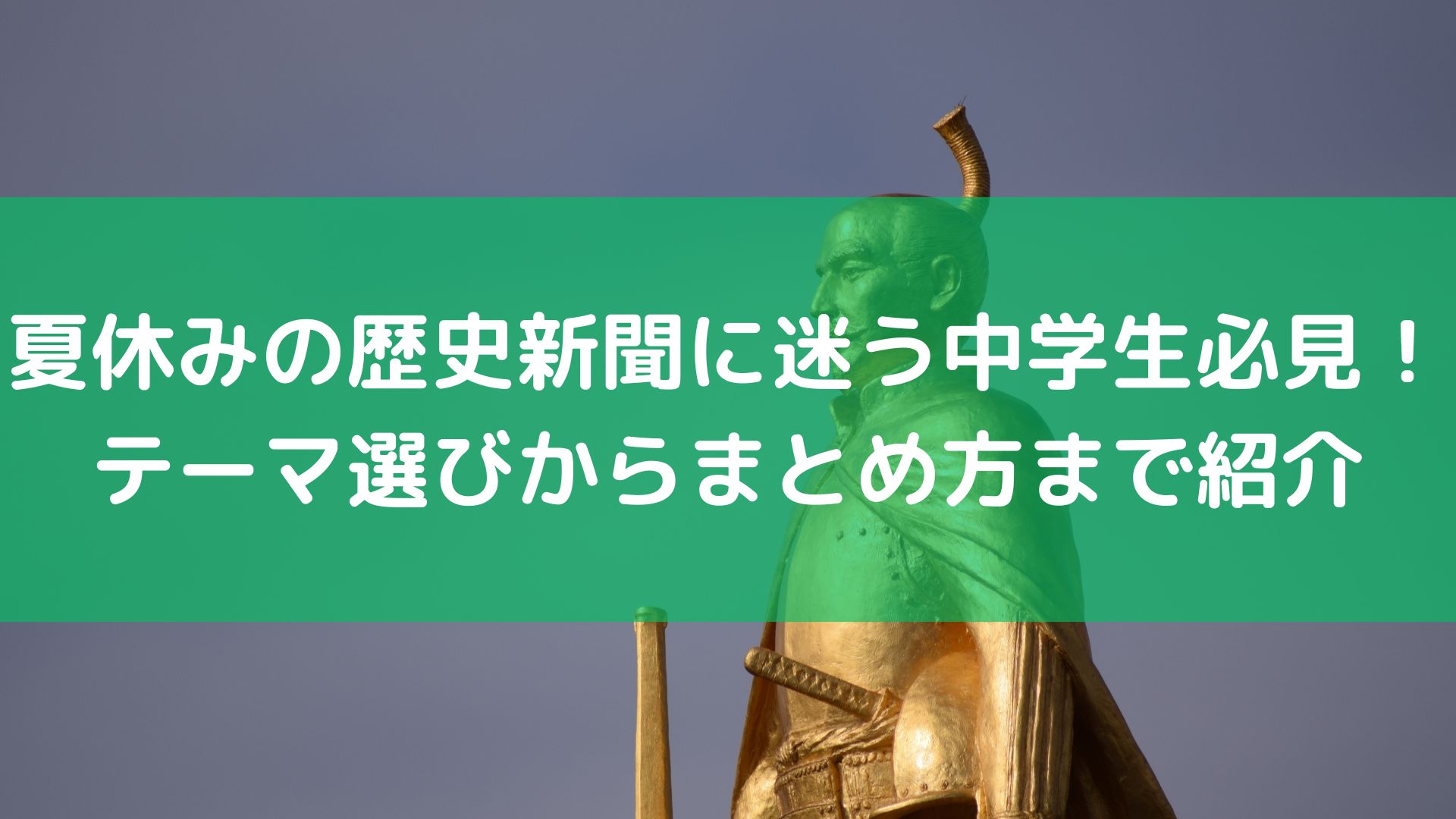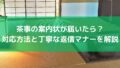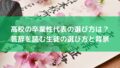「歴史新聞って、なにを書けばいいの?」
「好きな歴史人物はいるけど、新聞の形にまとめるのって難しそう……」
「テーマ選びって、どうやって決めたらいいの?」
そんなふうに、夏休みの宿題に手がつけられず困っている中学生のみなさんへ。
このページでは、歴史新聞をつくるときにぶつかりやすい「わからない!」や「むずかしい……」を、「できそう!」「やってみたい!」に変えるヒントをたっぷりお届けします。
まず大事なのは、調べやすくて書きやすいテーマをえらぶこと。
たとえば、歴史の授業でよく出てくる織田信長や明治維新などは、知っている人も多く、情報もたくさんあります。
でも、テーマを決めただけでは終わりません。
「まとめかたがわからない」「資料ってどこで見つけるの?」「見出しってどう作るの?」といった悩みがどんどん出てくるものです。
だからこそこの記事では、
-
テーマの選び方のポイント
-
おすすめの人物やできごとの例
-
まとめ方のコツや実例
-
資料を集める方法
などを、順を追ってやさしく紹介しています。
一緒にワクワクしながら「読んでもらえる歴史新聞」づくりにチャレンジしてみましょう!
歴史新聞ってなに?中学生にこそピッタリな理由とは
歴史新聞って、どういうもの?
歴史新聞とは、昔の人物やできごとを自分で調べて、新聞の形にしてまとめる学習のことです。
文章だけでなく、写真や地図、イラストなども使って見やすく工夫することができます。
この活動を通して、「調べたことを分かりやすく人に伝える力」や「自分の言葉でまとめる力」が身につきます。
新聞の形で発表するので、実際の新聞と同じように「見出し」や「レイアウト」も工夫して、伝わる工夫が学べるのです。
また、あとで誰かに読んでもらうことを前提に作るので、「どうしたら伝わるか」を考える力が自然と育っていきます。
どうして中学生に人気なの?
中学生にとって、歴史新聞は取り組みやすい宿題の一つです。
その理由は、自分の興味に合わせてテーマを決められるからです。
文章が苦手な人でも、図や資料を使って分かりやすくできるので、完成までのハードルが低く感じられます。
夏休みの宿題などでも、調べた内容を「誰かに伝える」ために工夫することで、プレゼンテーションの練習にもなります。
また、作り終わったときの達成感はとても大きく、「やってよかった!」という気持ちが残ります。
歴史新聞にピッタリなテーマ一覧
書きやすい歴史人物10人
歴史新聞に初めて取り組むなら、すでに授業で学んだことがある有名人物を選ぶのがおすすめです。
知っていることが多く、図書館やインターネットにもたくさんの情報があるので、調べやすくまとめやすいです。
以下の表は、中学生に人気のある歴史人物をまとめたものです。
この中から選べば、きっとスムーズに作業が進みますよ!
| 順位 | 歴史人物名 | ポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 織田信長 | 戦国時代を大きく変えた革命児 |
| 2位 | 聖徳太子 | 十七条憲法で知られる古代のリーダー |
| 3位 | 野口英世 | 医学で世界に貢献した偉人 |
| 4位 | 渋沢栄一 | 日本の資本主義の父 |
| 5位 | 卑弥呼 | 謎の多い女王として注目される |
| 6位 | 坂本龍馬 | 幕末のキーマンであり人気者 |
| 7位 | 紫式部 | 『源氏物語』を書いた平安時代の作家 |
| 8位 | 徳川家康 | 江戸幕府を開いた初代将軍 |
| 9位 | 豊臣秀吉 | 農民から天下人になった人物 |
| 10位 | 西郷隆盛 | 明治維新に関わった中心人物 |
比べながら選んで、自分が一番興味をもった人をテーマにしてみましょう。
調べがいのある歴史的できごとベスト10
人物ではなく、歴史の中の大きなできごとに注目するのもおすすめです。
物語のような展開があり、読み物としても面白くなります。
以下のようなできごとは、社会の流れを大きく変えたタイミングでもあります。
調べることで、「なぜそのできごとが大事なのか」がよくわかってきますよ。
| 順位 | 歴史的できごと名 | 主なポイント |
|---|---|---|
| 1位 | 明治維新 | 日本が近代国家へ進んだ大転換 |
| 2位 | 本能寺の変 | 信長の死が日本の歴史を大きく動かした |
| 3位 | 第二次世界大戦 | 日本と世界の関係が大きく変化した |
| 4位 | 関ヶ原の戦い | 日本全国が1つにまとまるきっかけに |
| 5位 | 日清戦争 | 外国との関係や日本の進歩が問われた戦い |
| 6位 | 平安京への遷都 | 日本の都が新しくなった出来事 |
| 7位 | 戦国時代の統一 | 各地の大名が争ったあと、国がまとまった |
| 8位 | 日露戦争 | 世界に日本の強さを示した戦争 |
| 9位 | 幕末の開国 | 日本が外国とつながり始めたとき |
| 10位 | 大政奉還 | 武士の時代が終わりを迎えた出来事 |
初心者におすすめのテーマの選び方
はじめて歴史新聞に挑戦するなら、なるべく「自分の知っていること」「調べやすいこと」から選ぶと安心です。
たとえば、地元のゆかりの人物や、過去に授業で興味を持ったテーマなどがおすすめです。
また、以下のような情報源を使うと、スムーズに進められます。
| 調べものに使える資料 | 特徴 |
|---|---|
| 学校の教科書 | 基本情報がまとまっていて安心 |
| 図書館の歴史関連の本 | よりくわしい情報がのっている |
| 信頼できるインターネット | 最新のデータや図表も見つかる |
最初は、資料が多くあるテーマから選んで、自信がついたら少しずつ広げていきましょう。
テーマ別に学ぼう!織田信長を使って書き方を理解しよう
織田信長の人生と功績をざっくり整理!
歴史新聞のテーマに織田信長を選んだら、まずは彼がどんな人だったのかを整理するところから始めましょう。
信長はどこで生まれて、どんな子ども時代をすごし、どんな戦いをして、何を目指していたのか――
そういったポイントを時系列で書き出してみると、新聞の流れが作りやすくなります。
たとえば、「桶狭間の戦い」や「比叡山焼き討ち」など、有名なできごとを簡単に紹介してみましょう。
それに加えて、「楽市楽座」や「天下布武」など、彼が行った改革や政策の意味を、わかりやすく説明できると、記事の深さがぐっと増します。
また、信長がどんな性格だったのか、なぜあれほど大胆な行動ができたのかを想像して書いてみるのもおもしろいですよ。
読み手の興味をひくためには、歴史上の人物を“生きた人”として伝える工夫が大切です。
信長をテーマにした新聞の組み立て例
実際に新聞を作るときは、記事の構成がとても大事になります。
歴史新聞は「見出し」「本文」「写真や図表」の3つのパートで構成すると、読みやすくなります。
以下は、織田信長を題材にしたときの新聞構成例です:
| パート | ポイント |
|---|---|
| 見出し | 「天下統一を目指した革新の武将」など印象的な表現にする |
| 本文 | 信長の人物像、行った政策、時代背景などをしっかり解説する |
| 図表 | 戦いの地図、年表、肖像画などを使って視覚的に伝える |
本文では、ただ事実を書くのではなく、「なぜその行動をとったのか」「その結果どうなったのか」を意識して書くと、深みのある内容になります。
図表や写真を活用すれば、言葉だけでは伝わりにくい情報も、グッとわかりやすくなりますよ。
資料や図表でわかりやすく伝えるには?
新聞記事をよりわかりやすくするためには、写真や図表の使い方も工夫が必要です。
たとえば、「桶狭間の戦い」の地図を載せれば、どんな場所でどのような戦いがあったのかが、イメージしやすくなります。
「本能寺の変」の年表を載せて、前後のできごとを時系列でまとめてみるのも効果的です。
信長の肖像画や、当時の京都や尾張の地図など、歴史の資料を使うことで、新聞の信ぴょう性もぐんと上がります。
資料は、本文の説明をサポートする役割も果たします。
配置する場所や大きさにも気を配って、見やすいレイアウトを意識しましょう。
そして、どこからその資料を持ってきたのか、出典元をきちんと書くことも大切です。
信頼される新聞に仕上げるための基本ですね。
歴史新聞を仕上げるためのステップガイド
見出しとレイアウトの基本を押さえよう
新聞の第一印象を決めるのは、見出しと全体のレイアウトです。
「夏休みの自由研究」として提出するなら、見た目もとても大切です。
タイトルは大きく目立たせて、サブタイトルで内容を補足する形にすると、伝えたいことがしっかり伝わります。
レイアウトは、段組をそろえたり、余白を均等にとったりするだけで、読みやすさがぐっとアップします。
装飾しすぎてしまうとごちゃごちゃして見えるので、シンプルだけど整ったデザインを心がけましょう。
見出しの色やフォントを少し変えるだけでも、紙面にメリハリが出て読みやすくなります。
写真・資料の集め方:信頼できる情報源を活用!
資料を集めるときは、インターネットだけに頼らず、図書館や地域の資料館などもぜひ活用してみましょう。
中学生の夏休みの宿題として使える、信頼できる資料がたくさんそろっています。
たとえば、地元の郷土資料館では、その地域にゆかりのある歴史人物の特別展示があることも。
また、教科書や学校図書館にある本も情報源としてとても便利で、先生からも評価されやすいです。
大切なのは、出典元を必ず書くこと。
「どこで見つけた情報か」が明らかになると、新聞全体の信ぴょう性が上がります。
それだけで、ぐっと完成度の高い作品になります。
見やすく伝わりやすい工夫をしよう
読者が読みやすいと感じる新聞にするためには、いくつかのポイントがあります。
まず、文章は長く書きすぎず、短く区切ってテンポよく書くようにしましょう。
もし難しい言葉が出てきたら、かんたんな説明や注釈をつけてあげると親切です。
写真や図表には、説明文を添えるだけで、情報の伝わり方が大きく変わります。
また、色の使い方やフォントの大きさを調整して、大事なところを目立たせる工夫もおすすめです。
読み終わったら、必ず全体を見直して、誤字や脱字がないかを確認しましょう。
そうした細かい気づかいが、新聞を読んでもらう人にやさしく伝わるはずです。
夏休みの歴史新聞に迷う中学生必見!テーマ選びからまとめ方まで紹介のまとめ
ここまで、歴史新聞をつくるためのステップやテーマの選び方、構成の工夫などをたっぷりと紹介してきました。
「やってみたいかも!」という気持ちが、少しずつ湧いてきたのではないでしょうか?
歴史新聞づくりは、むずかしく感じるかもしれませんが、大切なのは「自分の興味を出発点にすること」です。
まずはテーマを決めて、知りたいことをリストにしてみましょう。
調べるうちに、「こんなことがあったんだ!」という発見がきっとあるはずです。
新聞の形にまとめていく作業も、工夫しながらやればどんどん楽しくなっていきます。
見出しを考える、レイアウトを工夫する、図や写真で伝わりやすくする――そうした一つ一つの工夫が、自分だけの作品をつくるポイントです。
そして、完成した歴史新聞は、夏休みの思い出としても、自分の成長の証としても、きっと宝物になります。
自由研究や宿題という枠をこえて、学ぶ楽しさと「知るよろこび」を体験してみましょう。
この夏、自分だけの「歴史新聞」にチャレンジして、知らなかった歴史の世界へ一歩ふみ出してみませんか?