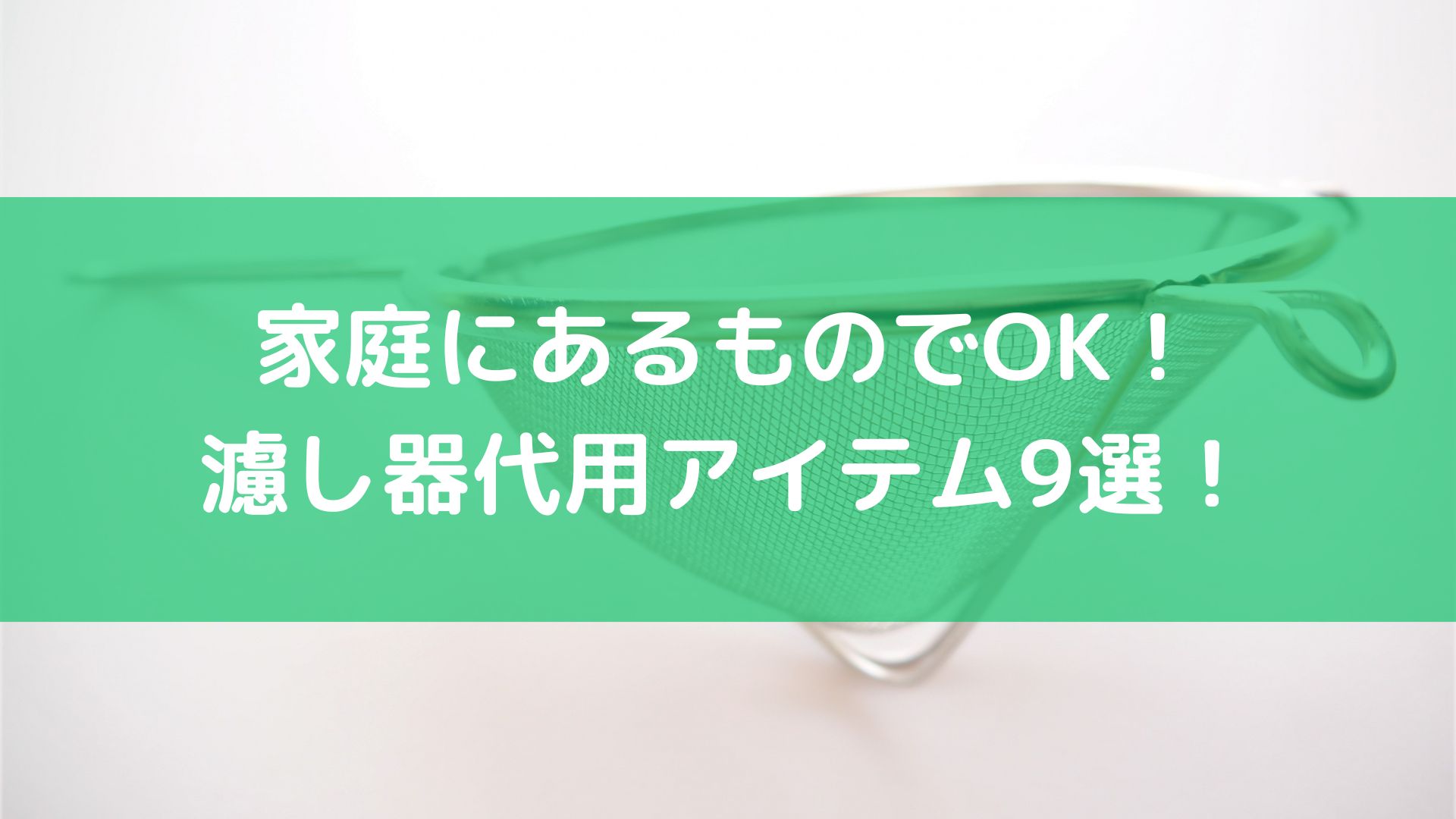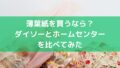プリンや茶碗蒸しなど、卵を使ったなめらかな料理を作るとき、一番大切なのは、なめらかな舌触りです。
そのためには、卵液の中にあるカラザやダマを、しっかりこして取り除く必要があります。
でも、日常的にこし器を使うことって、そんなに多くありませんよね。
だから、「こし器って持ってない…」という方もきっと少なくないはずです。
そんなとき、わざわざ専用のこし器を買わなくても、家にあるキッチンアイテムで代用することができます。
この記事では、こし器がない場合でも安心して料理ができるように、代わりになるアイテムや工夫、そして「こす」や「うらごし」といった作業の意味まで丁寧に解説していきます。
便利な代用品を知っておけば、急に「プリン作りたい!」となったときも、慌てずに対応できますよ。
「うらごし」ってなに?どんな役割があるの?
まず、「うらごし」という言葉を聞いたときに、具体的にどんな作業を指すのか、ピンとこない方もいるかもしれません。
うらごしは、食材を細かい網目の器具に押し付けて、よりなめらかで均一な状態に仕上げるための調理工程のことをいいます。
この工程では、スプーンやしゃもじで食材を押しながら、網の目を通してすりつぶすようにします。
例えば、かぼちゃやさつまいもなどの柔らかい食材を、ポタージュや離乳食にするときには欠かせない作業です。
うらごしをすることで、不純物やかたまりが取り除かれ、見た目もなめらかになり、口当たりもやさしくなります。
とくに赤ちゃんの食事や、のどごしが大切なスープ料理では、この工程がとても大切なんです。
また、うらごしのタイミングにもポイントがあります。
食材が熱いうちに行うことで、やわらかくスムーズにこすことができるため、仕上がりも格段に良くなります。
冷めてしまうと、材料がかたくなり、裏ごしするのに時間も手間もかかってしまいます。
「こす」と「うらごし」ってどう違うの?
「こす」と「うらごし」は、どちらも食材や液体を網などでこすという点では似ています。
でも、実際にはそれぞれに目的や使われるシーンに違いがあります。
「こす」というのは、基本的には不要なカスや固まりを取り除くための作業で、出汁をこしたり、粉をふるいにかけたりと、幅広く使われる表現です。
使う道具も、キッチンペーパーや茶こし、金属のザルなど様々で、用途に応じて選ばれます。
一方、「うらごし」は、なめらかな食感を作るために、特別に細かい網目の道具を使って、材料を丁寧にすりつぶしていく作業です。
たとえばプリンや茶碗蒸しなどの繊細な料理では、うらごしをすることで、舌触りが滑らかになり、料理の完成度がぐんと上がります。
つまり、「こす」は全体的に不純物を除く目的で、「うらごし」は食材自体をなめらかに変化させる作業というわけです。
「うらごし」は「こす」の中のひとつの形とも言えますね。
家にあるものでこし器の代用ができるアイテム
こし器が家になくても、キッチンにある身近なアイテムを使えば、十分に代用できます。
ここでは、料理のなめらかさを保つために役立つアイテムを、一つひとつ詳しくご紹介します。
茶こし
茶こしは、普段お茶を入れるときに使う道具ですが、その細かい網目を活かして、こし器の代わりにもなります。
特に卵液などの少量の材料をこしたいときには、とても便利で扱いやすいアイテムです。
持ち手がついているので安定して持てますし、手が汚れにくく、使い勝手が良いのも魅力です。
粉砂糖をふるったり、小麦粉を軽く均一にしたいときにも使えるので、お菓子作りにも重宝します。
ただし、茶こしはサイズが小さいため、一度に大量の材料をこすのには向いていません。
少量ずつ丁寧にこすことが求められますが、そのぶん繊細な仕上がりを実現できます。
あく取り
煮物やスープの上に浮いてくる「あく」をすくうための道具、あく取りも、こし器の代用品として使うことができます。
網目が細かく、浅めの形状をしているので、少量の卵液やスープをこすのに適しています。
ただし、あく取りはあまり深さがないため、材料が多すぎるとこぼれてしまう可能性があります。
少しずつ丁寧に作業する必要があるため、ゆっくりこす時間があるときに向いています。
見た目は地味ですが、意外と万能な道具のひとつです。
離乳食用こし器
離乳食用こし器は、赤ちゃんの食事を作るためのセットに含まれていることが多く、網目がとても細かく設計されています。
このため、少量の野菜や果物をなめらかに仕上げるのに非常に適しています。
サイズは小さいものが多いですが、そのぶん細かい作業に向いており、プリンの卵液やかぼちゃの裏ごしにも使えます。
離乳食づくり以外の場面でも、意外と出番の多い便利グッズです。
洗いやすくて軽い素材が多く、手軽に使えるのもポイントです。
小さな道具だからこそ、手間をかけて丁寧に料理したいときに力を発揮します。
スープこし器
スープこし器は、その名の通り、スープやだしをこすために作られた道具です。
網目が非常に細かく、食材のかすや細かい不純物をしっかりと除去してくれるのが特徴です。
卵液のような水分の多い材料をなめらかにしたいときにもピッタリで、プリンや茶碗蒸しなどの料理に活用できます。
一度にたくさんこすのには少し時間がかかるかもしれませんが、そのぶん仕上がりはとてもきれいになります。
やや大きめのサイズのものが多く、たっぷり作るときには特に活躍するアイテムです。
味噌こし器
味噌こし器は、味噌を溶かすために使う調理器具ですが、こし器としても十分に役立ちます。
特徴的なのは、その深さと、長めの持ち手がついている点です。
網目は少し粗めではありますが、柔らかい食材をこしたり、卵液を滑らかにしたりするには十分対応可能です。
安定感があり、ボウルに引っかけて使えるタイプも多いので、両手が使えてとても便利です。
丈夫な作りのものが多いため、繰り返しの使用にも耐える優れものです。
普段使っているザル
いつも使っているキッチン用のザルも、ちょっと工夫するだけでこし器の代わりになります。
ただし、ザルの網目が大きすぎると、細かい材料がこせなかったり、仕上がりが粗くなってしまう可能性があります。
そんなときには、ザルの中にキッチンペーパーやガーゼを敷いてからこすことで、網目を細かくして対応できます。
時間は少しかかりますが、丁寧に作業すればなめらかな仕上がりに近づけることができますよ。
キッチンにある身近な道具を上手に使って、工夫しながら料理の幅を広げていきましょう。
麺すくいザル
ラーメンやうどんなどをゆでた後、麺をすくうために使う「麺すくいザル」も、工夫すればこし器の代わりになります。
ただし、製品によって網目の大きさに違いがあるため、細かい材料をこすときは、網目の細かいものを選ぶことが大切です。
持ち手が長くて作業しやすいのがポイントで、手を熱湯から遠ざけられるため安全性も高いです。
卵液を少しずつ流しながらこせば、なめらかな仕上がりも期待できます。
ガーゼや布巾
薬局や家庭の掃除で使われるガーゼや布巾も、きれいに洗ったものや新品を使えば、立派なこし器の代わりになります。
特に、水分の多いものをこすときには、目が細かい布の方が、液体と固形物をしっかり分けられて便利です。
布の繊維が卵液の中の細かいカラザや固まりをしっかりキャッチしてくれるため、非常になめらかで美しい仕上がりになります。
ただし、布の使用後はしっかり洗うか、使い捨てのものを使うと衛生的です。
料理に使う場合は、調理専用として分けて使うようにしましょう。
粉ふるい
お菓子作りのときに大活躍する粉ふるいは、小麦粉やココアパウダー、砂糖などを均一にするための道具です。
この細かい目の構造を活かして、卵液をこすのにも利用できます。
特に、ハンドルを回すタイプの粉ふるいは、連続してこす作業がしやすく、手が疲れにくいのが嬉しいポイントです。
持ちやすい形状のものが多く、洗いやすさや軽さも魅力のひとつです。
料理の仕上がりにこだわりたい方には、意外と便利なアイテムになるでしょう。
卵液をなめらかにするための混ぜ方のコツ
こし器や代用品がしっかりしていても、卵液そのものがうまく混ざっていなければ意味がありません。
ダマや泡立ちがあると、プリンや茶碗蒸しの仕上がりに影響してしまいます。
卵を混ぜるときのコツは、「切るように混ぜる」ことです。
泡を立てずに、卵白のかたまりをゆっくりと分解するように、丁寧に動かしていきます。
ぐるぐる力強く混ぜるのではなく、箸を使って卵白を切り裂くような動きを意識しましょう。
そうすることで、泡立ちを抑えながら、なめらかな卵液ができあがります。
この混ぜ方と、しっかりしたこしの工程を組み合わせることで、見た目も口当たりも満足できる仕上がりになりますよ。
家庭にあるものでOK!濾し器代用アイテム9選のまとめ
「こす」や「うらごし」といった調理工程は、料理の見た目や味わいをぐんと引き上げてくれる大事なプロセスです。
プリンや茶碗蒸しのように、口当たりの良さが決め手になる料理では、手を抜けない部分でもあります。
こし器がなくても、茶こしやスープこし、粉ふるい、味噌こし器など、家にあるもので工夫すれば代用は可能です。
ガーゼや布巾などを使って、丁寧にこすこともできますし、ザルにキッチンペーパーを敷いて応用するのもおすすめです。
そして、卵液を混ぜる際は、泡を立てないように気をつけて、「切る」ように混ぜるのが成功の秘訣。
少しの工夫と丁寧な作業が、いつもの料理をワンランク上の仕上がりに変えてくれます。
今日から、あなたのキッチンでも、こし器がなくても大丈夫な工夫を取り入れてみてくださいね。