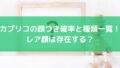最近、見知らぬ海外番号からの着信が増えていると感じることはありませんか?
特に「+28」で始まる電話番号からの着信が多発しており、不審に思う方が増えています。
この番号の発信元はどこなのか、そして電話に出てしまった場合、どのようなトラブルに巻き込まれる可能性があるのでしょうか?
結論から言うと、「+28」からの着信は詐欺電話である可能性が非常に高く、注意が必要です。
そこでこの記事では、「+28」の正体や危険性、そして被害を防ぐための具体的な対策について詳しく解説します。
不審な国際電話に関する知識を深め、ご自身やご家族を守るための参考にしてください。
最近増えている国際電話詐欺とは?「+28」からの着信の目的
近年、日本国内でも国際電話を悪用した詐欺が横行しています。
特に2023年以降、「+28」で始まる電話番号からの着信が増加しているという報告が相次いでいます。
私自身も「+28」からの着信を受けた経験があり、調べてみると、他にも同じような電話を受けた人が多数いることがわかりました。
ネット上の情報によると、「+28」からの電話では、「中国大使館からの重要なお知らせです」といった自動音声が流れることがあるそうです。
また、中国語のメッセージが流れる場合が多いものの、時にはカタコトの日本語で話しかけられることもあるとのこと。
こうした手口は、言葉が理解できる相手をターゲットにし、詐欺被害に巻き込むことを目的としていると考えられます。
さらに、留守番電話にメッセージを残すケースも報告されています。
このような国際電話は、詐欺グループによるものと考えられるため、着信があった場合は無視するのが賢明です。
「+28」ってどこの国?意外な事実が判明!
「+28」で始まる国際電話番号について詳しく調査したところ、この番号の大半は正式な国際電話番号として割り当てられていないことが判明しました。
唯一、「+282」が西サハラ(SADR)に割り当てられているものの、それ以外の「+28X」については、どの国にも正式に登録されていません。
この事実から、「+28」から発信される電話は、身元を隠すために未割り当ての番号を悪用している可能性が高いと推測されます。
また、一部では「+28」はベラルーシの国番号ではないかという情報が流れていますが、これは誤解です。
ベラルーシの国番号は「+375」であり、「+28」とは一切関係がありません。
この誤解は、「+28」がチャイルドシートの認可国コードとして使用されていることに由来していると考えられます。
つまり、「+28」からの着信は、正式な国際電話ではなく、何らかの不正行為に関連している可能性が高いのです。
怪しい国際電話への対処法!簡単にできる3つのポイント
知らない海外番号からの電話に出ることは、大きなリスクを伴います。
特に、詐欺グループが関与している可能性がある場合、適切な対策を取らなければ、思わぬ被害に遭う危険性があります。
そこで、誰でも簡単に実践できる3つの対策を紹介します。
知らない番号からの着信には出ない
見知らぬ番号から電話がかかってきても、すぐに出るのは避けましょう。
特に国際電話の場合、詐欺や高額請求のリスクがあるため、基本的には無視するのが最善の方法です。
電話がしつこく鳴る場合は、着信拒否を設定することで対応できます。
折り返しの電話はしない
国際電話の詐欺では、折り返し電話をさせる手口がよく使われます。
知らない番号からの着信履歴が残っていたとしても、決して折り返しをしないようにしましょう。
海外に知人がいる場合は、その番号が本当に知人のものか確認してから折り返すことが重要です。
折り返し電話詐欺の手口を理解する
詐欺グループは、折り返し電話をさせることで利益を得る仕組みを利用しています。
国際電話をかけると、日本の通信会社を通じて通話料金が発生し、その一部が発信元の海外の電話会社へ支払われる仕組みになっています。
詐欺グループはこの仕組みを利用し、海外の電話会社と連携して不正に利益を得ている可能性があります。
例えば、折り返し電話をすると、「しばらくお待ちください」といった自動音声が流れ、30秒ほど待つだけで数百円の料金が発生することもあります。
こうした手口によって、電話料金をだまし取られる被害が報告されています。
被害に遭わないためにも、心当たりのない番号には絶対に折り返さないようにしましょう。
迷惑電話対策に「着信拒否」や「ブロック」を活用しよう
最近、海外からの不審な電話が増えています。
見覚えのない番号からの着信があると、不安に思う人も多いでしょう。
特に、「+28」など、知らない国番号からの電話は注意が必要です。
こうした電話の中には、詐欺目的のものや、高額な通話料を請求されるケースもあります。
不審な電話には、安易に応答しないことが大切です。
しかし、何度も同じ番号から電話がかかってくると、無視し続けるのもストレスになりますよね。
そのような場合は、スマートフォンや固定電話の「着信拒否」や「ブロック」機能を活用しましょう。
本記事では、iPhoneやAndroid、固定電話の迷惑電話対策について、詳しく解説します。
iPhoneで迷惑電話をブロックする方法
iPhoneには、特定の番号からの着信やメッセージをブロックする機能が備わっています。
不審な番号をブロックするには、以下の手順を試してみましょう。
- 「電話」アプリを開く
- 画面下部の「履歴」タブをタップ
- 着信拒否したい番号の右側にある「i」アイコンをタップ
- 「この発信者を着信拒否」を選択
- 確認メッセージが表示されたら「着信拒否」をタップ
この設定を行うことで、指定した番号からの電話、メッセージ、FaceTimeの着信をブロックできます。
設定が完了すると、「この発信者を着信拒否」の表示が「この発信者の着信拒否設定を解除」に変わります。
iPhoneをお使いの方は、迷惑電話が続く場合にぜひ活用してください。
Androidスマートフォンで特定の番号を着信拒否する方法
Androidスマートフォンにも、特定の番号を着信拒否する機能があります。
機種やOSのバージョンによって、多少手順が異なる場合がありますが、一般的な方法は以下の通りです。
- 「電話」アプリを開く
- 「履歴」タブをタップし、着信履歴を表示する
- ブロックしたい電話番号を選択する
- 表示されたメニューから「番号をブロック」をタップする
- 確認メッセージが表示されたら「ブロック」を選択する
この設定を行うと、指定した番号からの電話やメッセージの受信が自動的に拒否されます。
また、一部のAndroid端末には、迷惑電話を自動で判別する機能が搭載されています。
迷惑電話の可能性がある場合に警告してくれる機種もあるため、活用するとよいでしょう。
固定電話やひかり電話での迷惑電話対策
スマートフォンだけでなく、固定電話やひかり電話にかかってくる迷惑電話も問題になります。
特に、国際電話を利用しない人にとっては、海外からの電話はほぼ不要なものです。
そこで、固定電話やひかり電話でも、迷惑電話を防ぐ方法を紹介します。
国際電話をブロックする方法
固定電話やひかり電話を使っている場合、「国際電話不取扱受付センター」(0120-210-364)に連絡しましょう。
この窓口に依頼することで、海外からの着信そのものをブロックできます。
国際電話を一切利用しない場合は、この方法を活用すると安心です。
通信キャリアの「国際電話ブロック機能」を活用しよう
頻繁に迷惑電話がかかってくる場合、通信キャリアのサービスを利用するのも有効です。
多くの携帯キャリアでは、国際電話の着信をブロックするオプションを提供しています。
以下の表に、大手キャリアの迷惑電話対策サービスをまとめました。
| キャリア | 提供されている迷惑電話対策サービス | 詳細 |
|---|---|---|
| NTTドコモ | 迷惑電話ストップサービス | 海外からの着信をブロックできる |
| au(KDDI) | 迷惑電話撃退サービス | 不審な番号を自動判別・拒否 |
| ソフトバンク | 国際電話拒否設定 | すべての国際電話をブロック可能 |
| 楽天モバイル | 不審な着信ブロック機能 | AIが迷惑電話を判断して警告 |
契約している通信会社の公式サイトに該当のサービスがない場合は、サポートセンターに問い合わせてみましょう。
また、不審な電話に出てしまうと、相手に「この番号は使われている」と認識される可能性があります。
そうなると、さらに多くの迷惑電話がかかってくるリスクがあります。
そのため、知らない番号には出ないようにすることが重要です。
まとめ:迷惑電話への適切な対策を心がけよう
不審な国際電話に対しては、慎重に対応することが必要です。
特に、「+28」など見慣れない国番号の着信には十分注意しましょう。
迷惑電話対策として、以下の3つのポイントを意識してください。
-
知らない番号には出ない
電話番号に見覚えがない場合は、無視するのが最も安全な対策です。
応答してしまうと、相手に「この番号は有効」と認識され、さらに迷惑電話が増える可能性があります。 -
折り返しの電話をしない
知らない海外の番号に折り返しの電話をすると、高額な国際通話料金が発生することがあります。
発信元に心当たりがない場合は、絶対に折り返さないようにしましょう。 -
着信拒否や迷惑電話ブロックを活用する
スマートフォンの「着信拒否」機能や、通信キャリアの迷惑電話対策サービスを利用すると、不審な電話を効果的に防げます。
迷惑電話は個人の問題だけでなく、家族や友人にも影響を与える可能性があります。
周囲の人にも迷惑電話の危険性や対策を共有し、詐欺被害を未然に防ぎましょう。