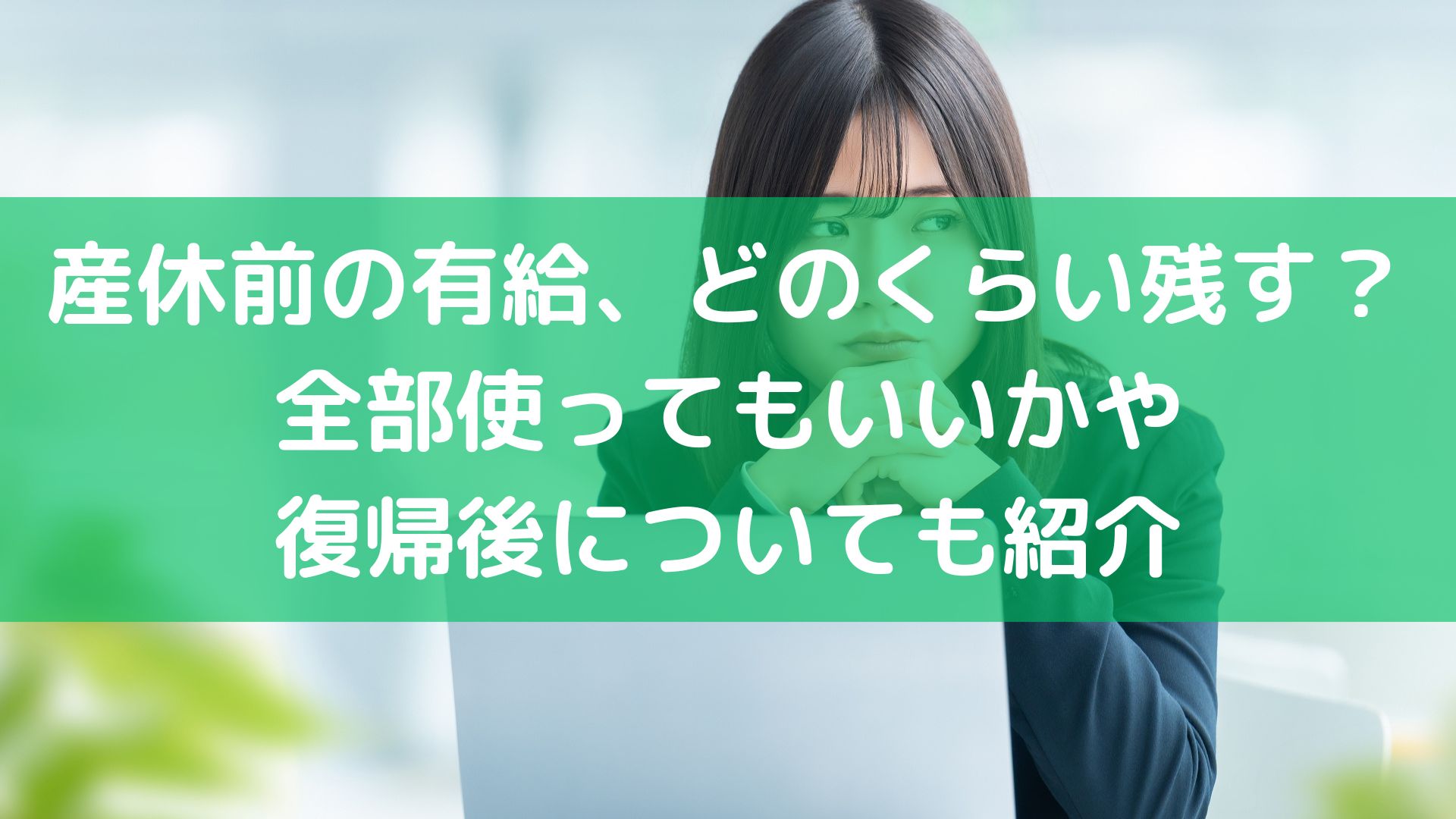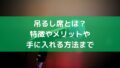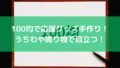出産前にお休みを取る予定の方へ、大切なお話があります。
それは、「有給休暇の使い方」についてです。
毎日忙しく働いていると、ついつい有給休暇のことを後回しにしがちです。
でも、そのままにしておくと、大切な日数が失われてしまうかもしれません。
とくに妊娠中は、体調が日によって大きく変わることもあります。
急な検診や体の不調などでお休みが必要になることもあるでしょう。
そんなとき、有給休暇がうまく使えると、とても安心です。
この記事では、産休前の有給休暇をどう使えばよいのかを、わかりやすくお伝えします。
-
有給休暇は全部使ってしまっても大丈夫なの?
-
それとも、少し残しておいた方がいいの?
-
お休みが終わって復帰したとき、有給はどうなっているの?
こんな疑問にこたえながら、あなたにぴったりの使い方をいっしょに考えていきましょう。
まずは現在の状況をチェックしましょう
最初にやるべきことは、「今、自分がどれだけ有給休暇を持っているか」を確認することです。
それがわからないと、どう使うかを考えるのがむずかしくなってしまいます。
そして、今ある有給休暇をそのまま放っておいたら、いつまで使えるのかも調べておきましょう。
有給休暇はずっと使えるわけではなく、使わなければ期限が来て消えてしまうのです。
「気づいたときにはもう遅かった…」ということがないように、今すぐ確認しておきましょう。
今の状況を知ることが、安心して出産や育児をむかえるための第一歩です。
有給休暇の基本を知っておこう
「お休みをしている間は、有給ってもらえないんじゃないの?」と不安になる方も多いと思います。
でも、安心してください。
実は、産休や育児休暇を取っている間も、法律では「出勤していた」と同じようにあつかわれます。
だから、次の年にもちゃんと有給がもらえるのです。
それでも、会社の決まりがあるかもしれないので、自分の職場の就業規則を見てみましょう。
書いていなくても、法律できちんと決まっていることなので、大丈夫です。
それから、有給休暇はずっとためておけるわけではありません。
通常は2年間たつと、使っていない分は自動的になくなってしまいます。
ただし、会社によってはもっと長く使えるようにしているところもあります。
そのため、自分の会社のルールをよく読んでおくと、あとであわてずにすみますよ。
現在の有給残数を把握しよう
「いったい自分は今、有給が何日残っているの?」
それを正しく知ることが、とてもたいせつです。
たいていの会社では、パソコンやスマホから勤怠管理システムにアクセスすると、有給の残り日数がすぐにわかります。
もしシステムが使えないときは、遠慮せずに総務部や人事部に聞いてみましょう。
「だいたいこれくらいだった気がする」というあいまいな記憶では、正しい計画が立てられません。
きちんとした数字を知っておくことで、産休前のスケジュールも安心して立てられます。
今の時点で何日あるのか、いつまでに使う必要があるのかをはっきりさせましょう。
付与日と日数のルールを確認しよう
次に確認したいのは、「いつ、何日分の有給休暇がもらえるか」です。
これは、会社によって少しずつちがいます。
たとえば、次のようなルールがあるかもしれません。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 有給がもらえる日 | 入社から半年たった日/毎年4月に一斉/決算月の翌日など |
| もらえる日数 | 勤めている年数によって変わる(6年半以上で20日など) |
休業後に有給はどうなる?復帰時の想定
「出産や育児で長く休んだら、有給ってもらえるの?」と心配になりますよね。
でも、大丈夫です。
さきほどもお話ししたように、産休や育休中は「出勤していた」として有給の計算にふくまれます。
だから、休んでいる間にも次の有給がもらえるのです。
ただし、気をつけなければいけないのは「消えてしまう有給」があることです。
さきほどのとおり、有給休暇には2年の期限があります。
つまり、今もっている有給の一部が、復帰するころには期限切れでなくなってしまうかもしれません。
そのため、あらかじめ消滅しそうな日数を確認しておき、必要なら前もって使っておくことがたいせつです。
どのくらい使うべき?有給の使い道を考えよう
それでは、有給は全部使いきったほうがいいのでしょうか?
それとも、少し残しておくべきでしょうか?
ここは、あなたの今後の予定に合わせて、よく考える必要があります。
たとえば、今30日ぶんの有給があって、次に4月に20日もらえるとしましょう。
育児休暇を1年取るとすると、復帰するころには10日ぶんが消滅する可能性があります。
このような場合は、「なくなる前に使ってしまう」のがよい選択になるかもしれません。
でも、「子どもが保育園に入れるか分からない」「復帰の時期がまだはっきりしない」といった人は、すこし残しておく方が安心です。
このように、自分の予定や会社のルールを見ながら、使う日数や残す日数をしっかり考えておきましょう。
有給休暇は使い切るべき?それとも少し残す?判断のポイントを知ろう
「あと10日ほど有給が残っているけれど、使い切るべきか迷う」
そんな声をよく耳にします。
基本的には、有給休暇は使わないままでいると消滅してしまうことが多いです。
特に、取得期限が近いものがあれば、優先的に使っておくのが損をしないコツです。
たとえば、10日分の有給が残っているなら、それを産休の前にすべて使ってしまえば、実質的に2週間前倒しで休みに入ることができます。
心にも体にもゆとりをもって準備できるので、多くの方にとって有効な方法といえるでしょう。
もちろん、会社や部署の忙しさ、チームの状況もあるかもしれません。
ですが、有給休暇は労働者に認められた権利ですので、遠慮しすぎる必要はありません。
一番大切なのは「自分の体調や準備の都合に合わせて」計画的に使うことです。
急にお腹が張ったり、つわりがひどくなったりする場合もあるので、前もって休みを取っておくと安心です。
また、引き継ぎやマニュアル作成の時間として有給休暇を使うのも有効です。
きちんと引き継ぎができれば、職場の人たちも安心して送り出してくれるでしょう。
産前休業をすぐに取らず、有給で調整するのもひとつの方法
出産予定日の6週間前から「産前休業」に入ることができます。
でも、「必ずその日から休まなければならない」というルールではありません。
「体調が安定しているから、もう少しだけ働きたい」
「引き継ぎがまだ終わっていないので、あと数日勤務したい」
そんなときには、有給休暇を使って休みに入る日を自分で調整することができます。
出産手当金と有給休暇のどちらがお得か、収入面で比較してから決める人も増えています。
どちらが自分にとってベストか、少し計算してみましょう。
柔軟に取れる産前休業、実は自由度が高い制度です
産前休業は、最大で出産予定日の6週間前から取ることができる制度です。
でも、これは「最長」であって「必ず取らなければいけない期間」ではありません。
実際には、働けるうちは出勤を続けても良いのです。
自分の体調と相談しながら、必要な時期に必要な分だけ休むという考え方でOKです。
出産予定日が近づいてくると、通勤だけでもつらくなることがあります。
そんなときは、有給休暇を1日ずつ使って、少しずつ体を休ませるのも良い方法です。
有給休暇と出産手当金の違い、わかりやすく比較
有給休暇を使う場合と、産前休業を取って出産手当金を受け取る場合では、もらえるお金に違いがあります。
出産手当金は、ざっくりといえば「標準報酬日額の約3分の2」が支給されます。
これは基本給に基づいた計算ですので、残業代などは含まれません。
一方、有給休暇を使えば、通常どおり1日分の給与が支給されます。
そのため、単純に金額だけを比べると、有給休暇を使ったほうが収入は多くなるケースが多いのです。
以下のように、具体的に比べてみるとわかりやすくなります。
| 比較項目 | 有給休暇 | 産前休業(出産手当金) |
|---|---|---|
| 支給される金額 | 日給100%(残業手当含む場合あり) | 標準報酬日額の約67%(残業除く) |
| 社会保険の扱い | 保険料免除(勤務扱い) | 保険料免除 |
| 賞与への影響 | ほぼなし(勤務扱い) | 勤務日数に応じて減少の可能性 |
有給休暇を使って産前休業を短縮?上手な使い方を考えよう
すべての有給休暇を使い切るのが難しいときもあると思います。
そんなときは「産前休業の一部を短縮して、そのぶん有給でカバーする」という方法もあります。
これにより、出産手当金の支給期間は少し短くなりますが、金銭的な損失を最小限に抑えることができます。
また、有給休暇を使えば賞与への影響も出にくくなるので、長期的に見てもメリットがあります。
職場によっては、有給休暇の取得が評価にプラスになるケースもあるので、気になる場合は人事に確認してみてもよいでしょう。
産休前の有給、どのくらい残す?全部使ってもいいかや復帰後についても紹介のまとめ
これまで解説してきたように、産休に入る前の有給休暇の使い方には、たくさんの選択肢があります。
大切なのは「自分の体調」や「仕事の進み具合」に合わせて、無理のない形で計画を立てることです。
そして、有給休暇が消滅しないように、早めにスケジュールを確認しておくことが重要です。
また、収入面でも手当金と比較することで、どのように休暇を取れば得かが見えてきます。
賢く制度を使えば、出産までの期間を安心して過ごすことができるでしょう。
もちろん、権利として休むことは正当なことですが、会社や同僚の協力を得るためには「多少の配慮」も必要です。
引き継ぎを丁寧に行うなど、思いやりある行動を心がければ、産休後の復帰もスムーズになります。
一人で悩まず、会社の総務や先輩ママにも相談しながら、ぜひ自分に合った働き方・休み方を見つけてください。