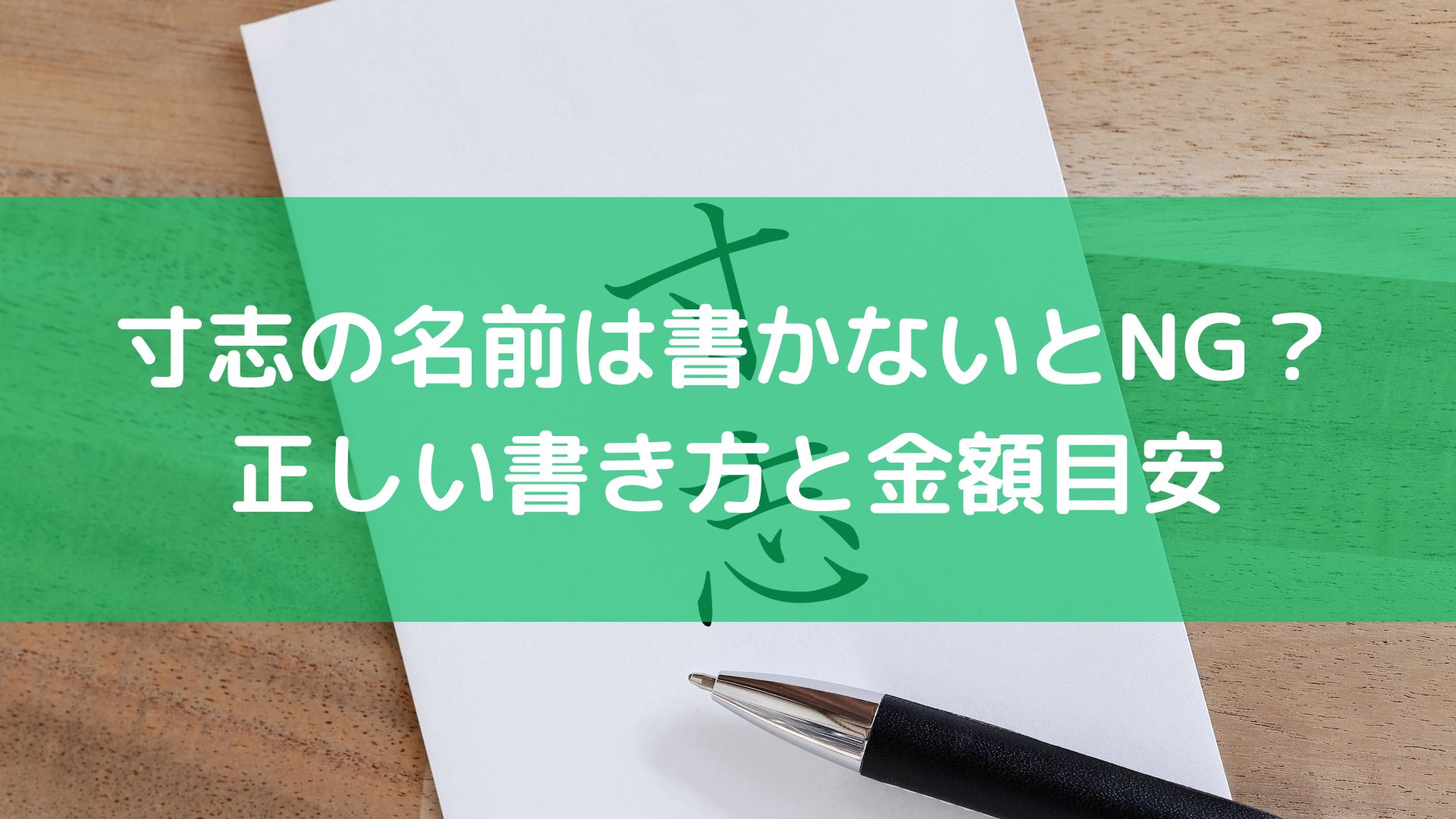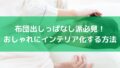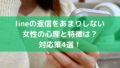会社の行事や職場のイベントで、ちょっとしたお礼や感謝の気持ちを現金で渡すときがあります。
そのようなときによく使われるのが「寸志(すんし)」という形です。
でも、「封筒に自分の名前を書くの?」「表書きってどう書けばいいの?」と迷うこともありますよね。
また、どれくらいの金額を包めばいいのかや、いつ渡すのが良いのかも気になるポイントです。
この記事では、寸志を渡すときに必要なマナーや書き方について、わかりやすく丁寧に解説します。
初めて寸志を渡す方でも安心できるように、順を追ってご紹介していきます。
寸志の封筒には名前を書くのが正解?基本マナーを解説
寸志を誰かに渡すとき、封筒に名前を書くべきかどうかは、よくある疑問のひとつです。
先に結論をお伝えすると、「名前は書きます」。
寸志を渡すときには、封筒の表や裏、あるいは中袋に、送り主の名前を書くのがマナーとされています。
使用する封筒は、普通の白い封筒でも問題ありません。
ただし、できれば中袋が付いた寸志用の封筒を選ぶのが安心です。
最近では、100円ショップや文具店などでも簡単に手に入るので、入手には困りません。
封筒のデザインにもいくつか種類があります。
寸志用としてよく使われるのは「花結び(水引が蝶結びのもの)」が印刷された封筒です。
この封筒がない場合は、赤い線が1本引かれた「赤棒のし袋」と呼ばれるシンプルなものでも構いません。
白い封筒を使う場合も、表書きの書き方さえ守っていればマナー違反にはなりません。
このあとの項目で、具体的な書き方や記入場所について、さらに詳しく説明します。
寸志の封筒はどこに何を書く?表書き・裏書き・中袋の正しい方法
寸志を入れる封筒には、「表書き」「裏書き」「中袋」それぞれにルールがあります。
どの部分に何を書くべきか、下の表にまとめました。
| 書く場所 | 書く内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 表(表書き) | 中央上部に「寸志」、下に名前 | 筆ペンまたは黒のサインペン使用 |
| 裏(裏書き) | 氏名と住所(中袋がないときのみ) | 金額は不要 |
| 中袋(内袋) | 氏名と住所(中袋がある場合)、金額欄あり | 金額は書かなくてもOK |
表書きの書き方
封筒の表面には、まず中央の上部に「寸志」と大きく書きます。
文字は、筆ペンや濃い黒のサインペンを使いましょう。
続いて、「寸志」と書いたその下に、送り主の名前を記入します。
会社名も記載する場合は、個人の名前の右側に少し小さめの文字で「株式会社○○」と書きます。
法人格も省略せず、正確に記入するのが丁寧です。
なお、相手が目上の人であれば「御礼」や「御挨拶」「謝儀」と書くこともあります。
このあたりは関係性やシーンによって使い分けましょう。
裏書きの書き方
中袋がない場合は、封筒の裏面に自分の名前と住所をきちんと書きます。
金額については、寸志や御礼の封筒には基本的に書きません。
これは、寸志があくまで「見返りを求めない気持ち」を表すものだからです。
中袋のある場合
中袋がある場合は、そこに送り主の名前と住所を記入します。
中袋には金額を書く欄もありますが、書かなくても問題ありません。
ただし、金額を書くことで受け取る相手にとっても管理しやすくなるというメリットはあります。
心付けを小さなポチ袋で渡す場合は、「心付け」と表に記し、裏面には氏名を入れると丁寧です。
かわいらしいデザインのポチ袋を選ぶと、場も和みますよ。
寸志はいくら包む?金額の目安を状況別に解説
寸志に包む金額は、場面や自分の立場によって大きく変わります。
「いくらくらい包めば失礼がないのか?」と悩んだときは、以下の表を参考にしてください。
| シチュエーション | 相場の金額 |
|---|---|
| 歓迎会・送別会・慰労会 | 1,000円~5,000円程度 |
| 結婚式のヘアメイク・着付けへ | 3,000円~10,000円程度 |
| ホテル・旅館などでの心付け | 1,000円~3,000円程度 |
一方で、同じ立場の同僚同士で渡す場合は、会費と同じくらいの額で問題ありません。
また、心付けについては日本のホテルや旅館では基本的に不要です。
すでにサービス料が含まれていることが多いためです。
ただし、外資系のホテルなどでは受け取ってくれる場合もあるので、渡すタイミングと状況には注意が必要です。
寸志を渡すベストなタイミングとは?ケース別に紹介
寸志は、ただ渡せばよいというわけではありません。
「いつ渡すか?」というタイミングも非常に大切です。
歓送迎会・慰労会の場合
会社のイベントなどでは、会が始まる前に幹事へ寸志を手渡すのがもっとも適切です。
イベント中や終わってから渡すと、相手の手がふさがっていたり、会計がややこしくなる可能性があります。
開始前の静かなタイミングを見計らって、さりげなく渡すのがマナーです。
結婚式でスタッフへ渡す場合
ヘアメイクや着付けを担当してくれるスタッフには、作業前に渡すのがベストです。
感謝の気持ちを前もって伝えておくことで、コミュニケーションもスムーズになります。
また、複数人で寸志を贈る場合は、表書きに「○○一同」や「有志一同」と記載し、別紙でメンバーの名前を添えるのが一般的なマナーです。
寸志とは?感謝を伝える控えめな贈り物
「寸志(すんし)」という言葉には、「わずかばかりの志」という意味が込められています。
これは相手に対して、あくまでも控えめに、感謝や労いの気持ちを表すための言葉です。
日常的には、部下へのお礼や歓送迎会、ちょっとした協力への感謝として用いられることが多いです。
特に日本のビジネス文化では、目上の人が目下の人へ寸志を贈るという流れが長く続いてきました。
最近では、白い封筒だけでなく、コンビニや100円ショップなどでも「寸志」と印刷された封筒が簡単に手に入るようになっています。
ただし、寸志は気持ちの贈り物なので、あまりにも高額になったり、派手な包装をすると、かえって相手に気を使わせてしまうこともあるので注意が必要です。
金額や包装の派手さではなく、「心がこもっているか」が最も大切なポイントになります。
寸志を贈るときのマナーと表現の使い分け
寸志は基本的に、立場が上の人から下の人に対して贈るものである、という点をまず押さえておくことが重要です。
ですから、自分よりも上司や先輩に感謝を伝えたい場面では、「寸志」という言葉は使わないようにしましょう。
そのような場合は、「御礼(おんれい)」「御挨拶(ごあいさつ)」「謝儀(しゃぎ)」といった表現を選ぶ方が適切です。
誤った表現を使ってしまうと、失礼にあたる可能性がありますので、注意が必要です。
例えば、町内会のお手伝いに対してお金を渡す場合や、お祭りでのお花代を包む場合などは、また別のマナーがあります。
そういったケースでは、状況に合った表現や金額が必要ですので、他の記事などを参考にするのがおすすめです。
表現の使い分けひとつで、印象が大きく変わるということを覚えておきましょう。
寸志に名前を書くべき?封筒の表書き・裏書きの基本
「寸志を贈るとき、封筒に自分の名前を書かない方がいいのでは?」と迷う方もいるかもしれません。
ですが、基本的には「名前は必ず書くべき」です。
封筒の表には、「寸志」と書き、その下に贈り主のフルネームを書くのが正式なマナーです。
また、封筒の裏側には、必要に応じて金額や日付、部署名などを記入すると、より丁寧な印象になります。
受け取る側も誰からの寸志なのかがすぐにわかるので、安心して受け取ることができます。
以下に封筒に記載する内容を表にまとめました。
| 封筒の場所 | 書くべき内容 |
|---|---|
| 表面 | 「寸志」の表書きとフルネーム(縦書き) |
| 裏面 | 金額、日付、部署名(必要な場合) |
寸志の相場と封筒選びのポイント
寸志に包む金額は、状況や相手との関係によって異なりますが、以下のような目安があります。
| シーン | 金額の目安 |
|---|---|
| 歓迎会・送別会 | 1,000円〜5,000円 |
| 結婚・昇進などのお祝い | 5,000円〜10,000円 |
| 簡単なお礼や手伝いへの感謝 | 500円〜3,000円 |
寸志の正しい渡し方とタイミング
寸志を渡すときに大切なのは、「形式だけにこだわらず、気持ちを込めること」です。
渡すタイミングとしては、歓迎会の冒頭や中締めのタイミングなどが一般的です。
会が終わる頃にバタバタと渡すのではなく、落ち着いたタイミングを見計らうのがスマートです。
封筒は必ず両手で持ち、表書きが相手に見える向きで渡しましょう。
その際、「ささやかですが」「ほんの気持ちです」などの一言を添えると、より丁寧な印象になります。
形式的になりすぎず、気持ちがしっかり伝わるようにすることが大切です。
寸志の名前は書かないとNG?正しい書き方と金額目安のまとめ
寸志は、金額の多寡よりも「感謝の気持ちを伝える」という姿勢が重要です。
封筒の選び方や名前の記入など、基本的なマナーを押さえていれば、誰でも安心して贈ることができます。
また、「寸志」という言葉自体が目上から目下へ向けたものであることを忘れずに、使う場面には十分注意しましょう。
正しいマナーで寸志を渡すことができれば、相手との関係もより良好なものになります。
このような日本独特の気配りの文化を大切にしながら、感謝の気持ちをしっかりと伝えていきたいですね。